
8月5日は「タクシーの日」!!
みなさん、ご存知でしたか?
へぇ~~なるほど!タクシーにまつわる豆知識。
目次
8月5日は「タクシーの日」
由来
日本のタクシーは、1912年(明治45年)7月10日、東京銀座の数寄屋橋に「タクシー自働車株式会社」が設立され、同年8月5日にアメリカ製のT型フォード6台で営業を開始したのが始まりです。(※日にちは諸説あり。)
料金メーターを搭載しており、「辻待ち自動車」と呼ばれていました。
日本初のタクシー営業始まりの日を記念して、一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会が1989年に8月5日を「タクシーの日」と定めました。
「辻(つじ)待ち」という言葉は、人力車や馬車が客を待つ様子を表す言葉として使われていましたが、自動車の普及に伴い、自動車が客を待つ状態にも使われるようになりました。
「辻」は、道路が交差する場所、四つ辻を意味します。
自働車か自動車か
当時は「じどうしゃ」には「自動車」と「自働車」の二通りの表記がありました。
日本に自動車が入ってきた当時から、両者は混在しつつも人が動かすのだから人偏がつくべきという考えから自働車という表記がやや優勢でしたが、やがて自動車へと統一されました。
タクシー自働車株式会社の設立時には自働車か自動車かだけではなく、タクシーをどう表現するかも問題となりました。
当初はタクシーを辻待人力車にならって「辻待自働車」という名称も考えられていました。
しかし、原語にあわせてTAXIを採用することになりました。
カタカナ表記するにあたっても「タクシー」か「タキシー」かも問題になったといいます。
もしかしたら、タクシーではなくタキシーになっていたかもしれませんね。
タクシーの歴史
タクシーは、人々がより便利に移動できるように、馬車や人力車に代わる交通手段として登場しました。特に、自動車の技術革新と、それによる移動手段の多様化がタクシーの発展を後押ししました。
馬車
昔は、馬車が主な移動手段でした。
古代から中世、近世にかけて、世界中で広く使われた乗り物です。特に、ヨーロッパでは貴族の移動手段や、都市間輸送、郵便配達などで活躍しました。
日本では、明治時代になってから本格的に導入され、郵便馬車や乗合馬車として利用されました。
馬車は、人や荷物を運ぶために使われ、運賃を徴収する馬車も現れ、タクシーの原型として活躍したのです。
人力車
日本では、江戸時代から駕籠(かご)や人力車がタクシーのような役割を果たしていました。
人力車は、明治時代に日本で発明され、庶民の交通手段として広く利用されました。しかし、鉄道や自動車の普及に伴い、次第に姿を消していきました。
現在では、観光客向けの乗り物として、主に浅草や京都などの観光地で利用されています。
人力車を引く人を「車夫」と呼び、通常は一人で引きますが、二人以上で引いたり、交代要員の車夫が併走したりすることもあります。
浅草や京都の人力車は、外国人観光客にも人気があり、観光案内をしながら撮影スポットで写真撮影をしてくれたり、思い出作りを担ってくれる存在として親しまれています。
1914年以降
1914年になると、東京駅の開業や第一次世界大戦の開戦もあり、タクシー業界は盛り上がります。そして全国でタクシー会社が次々と設立されるようになりました。しかし、料金形態がバラバラで苦情が殺到。
これを受け大阪市では、1924年に1円均一タクシー(通称:円タク)を導入します。その2年後には東京都でも円タクが運行されるようになり、タクシー業界は発展をしていきました。
1931年の満州事変により、日中の関係が危ぶまれる中、石油会社が値上げを発表します。
1938年になると、警視庁がタクシー営業のルールを制定(最低基準車両50両)し、多くのタクシー業者が廃業、または統合することになりました。
その後、第二次世界大戦が勃発し、石油資源確保のためにタクシーの流し営業が禁止になります。そのため戦時中は、木炭などが燃料として使われるなど苦しい状況が続きました。
戦後1950年代になると、自動車の性能が上がり「神風タクシー」が世間を賑わせるようになります。
「神風タクシー」とは、粗暴運転や乗車拒否、不当請求などを行う悪質なタクシーで、交通事故も増え社会問題となりました。
ドアが自動ドアに
自動ドアになるまでは、助手席にも乗務員がいて、その人がドアの開閉やお手伝いをしていました。
しかし高度経済成長でタクシー需要が高まると、運転手から「運転席でドアが開閉できたら嬉しい」「乗客がドアを開けて後続車と接触するトラブルが絶えない」という声が出るようになります。
そこで愛知県のトーシンテック(現在国内シェア9割)が開発に乗り出し、自動ドアを販売まで漕ぎ着けました。
ところがタクシー業界は「自動ドアは贅沢だ」「楽をするなんてみっともない」という考えが根付いており、導入するタクシー会社は少数でしたが、1964年に東京オリンピックの開催が決まり、タクシーの需要が高まることが確実になります。
その結果「ここで日本のタクシーのおもてなしをアピールしよう」と考える会社が増え、自動ドアが一気に普及しました。
そこからタクシー業界はサービス競争が始まり、全国的に自動ドアが当たり前になったのです。
生誕100周年
2012年にタクシー生誕から100年となりました。同年にはスカイツリーの開業で国内外から観光客が押し寄せました。
タクシー業界では、近年、環境に配慮した車両の導入が進められています。ハイブリッド車や電気自動車などの次世代自動車の普及を推進し、カーボンニュートラル実現に向けた取り組みが進められています。
「タクシーの日」のキャンペーン
毎年、「タクシーの日」には、全国各地でキャンペーンが実施されます。タクシー業界のPR活動や、タクシーに関する理解を深めるためのイベントなどが開催されます。
大阪では、8月2日に「タクシーの日スペシャル in 大阪」というイベントが開催されます。このイベントでは、タクシー車両の展示や、ラジオ番組とのコラボ企画など、様々な催しが予定されています。
「助手席」はタクシー用語
みなさんが日常的に使う「助手席」という言葉。実はタクシー業界の用語だそうです。
昔は着物を着た人が多く、またドアが自動になる前は、乗車や降車のドアの開閉をお手伝いする人が必要でした。そのため運転手の隣に「助手さん」と呼ばれる人が乗車していました。
そこから助手席と呼ばれるようになり、一般人にも浸透していきました。
おもしろ専門用語
●あんこ
駅待機のレーン等で前後に挟まれて出られない事。 「たこつぼ」とも言う。
●おばけ
長距離利用客、特に意外な場所や時間帯で長距離を希望するお客さまのこと。滅多に遭遇しないため、珍しい、嬉しいという意味合いで使われます。
●コロ
近距離のお客さまの呼称。一説によれば「タイヤがコロコロと動いたくらいのお客さま」という意味なのだとか。
●ゾンビ
タクシーが捕まりにくい状況で、道端で多くの人がタクシーを求めて手を上げている様子を指します。特に、金曜の深夜や連休前など、タクシー需要が高まる時間帯によく見られます。
●天ぷら
「タクシーに4人乗車したとしても1,000円以内の距離で全員降りてしまうこと」を言います。このような状況はお客さまが多い割に売り上げが伸びないのが悩みの点です。
●ネギ
「お客さまからの苦情」のことを言います。 京都で有名な、九条ネギの九条と苦情をかけて使われるようになったようです。
●マグロ
流し専門(走行してお客さまを探す)のドライバーをさします。 一説によれば、マグロは泳いでいないと窒息することから、流し専門のドライバーをマグロに見立ててこのように呼ぶようになったようです。
●わかめ
「回送」と「海草」をかけたダジャレ。
時代の流れとともに進化し続けるタクシー業界では、業界用語は馴染みの薄いものになりつつあるそうです。

参考:https://p-chan.jp/taxi/column/history,https://media.mk-group.co.jp/entry/taxi-history-day/
まとめ
「タクシー」が「タキシー」になっていたかもしれないとは、ビックリですね!
タクシーにまつわる雑学、いかがでしたか?
最近では、社会貢献がしたい、お年寄りの役に立ちたいなどの思いで、タクシードライバーになる方も増えているそうです。


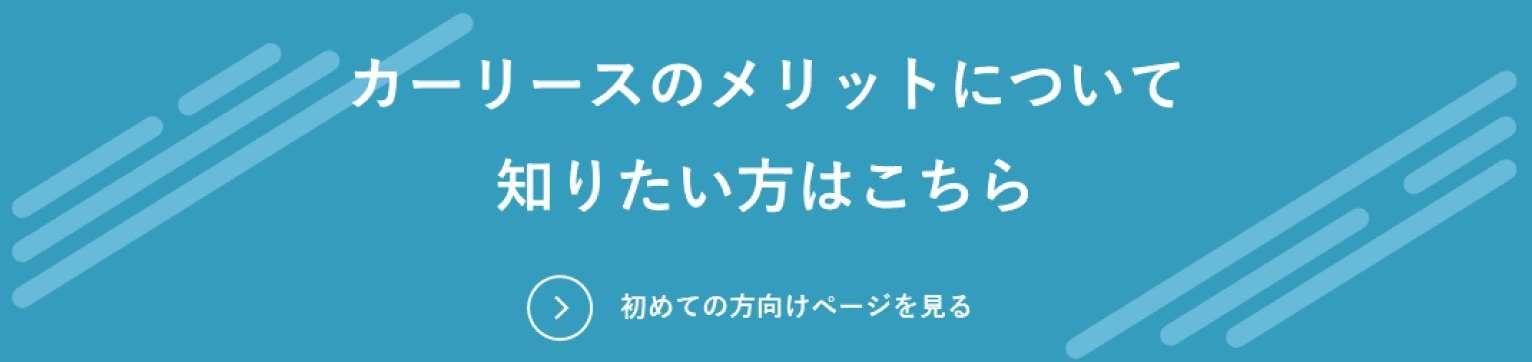

 前の記事
前の記事


